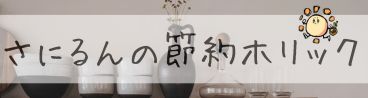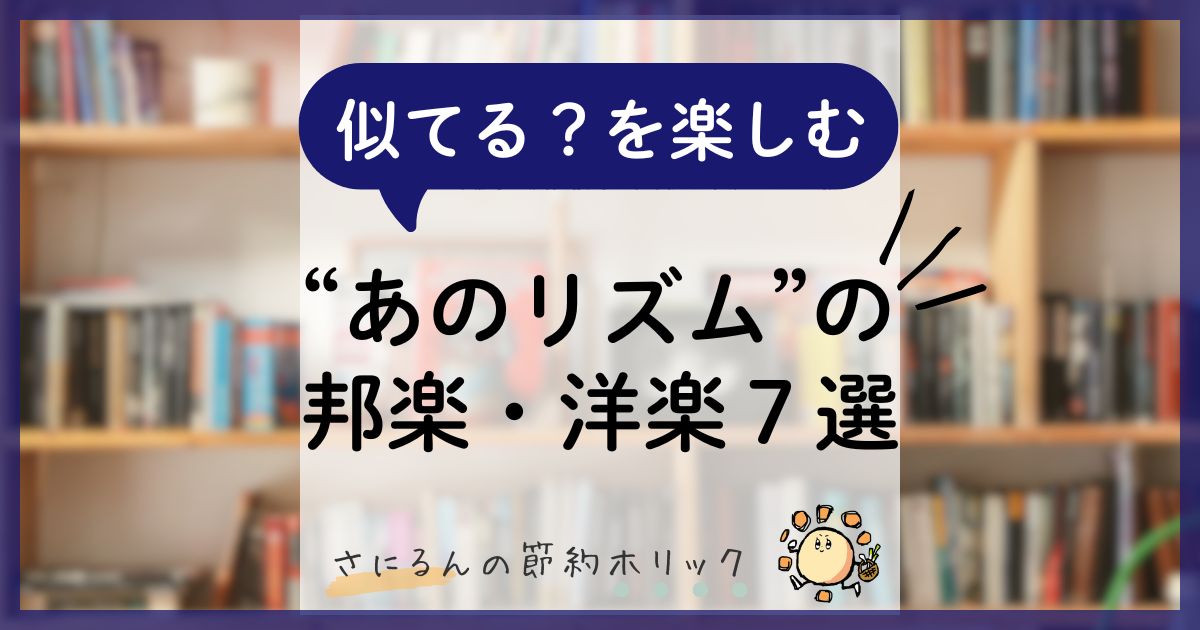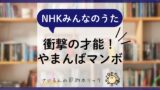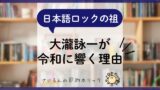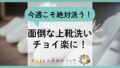こんにちは!久々の音楽の記事です。
前回は、折坂悠太さんがNHKみんなのうた「やまんばマンボ」(2025年)で民謡とラテン音楽を融合させた驚異的なセンスについて熱く語りました。
細野晴臣さんのトロピカル三部作を彷彿とさせる、と言っても過言ではないでしょう。
その前の記事では、日本のロック黎明期にブラック・ミュージックのリズム感を独自の形で昇華させた大瀧詠一さんの天才性について触れました。
東洋的なルックスからは想像もつかない、あのグルーヴィーな感覚は本当に面白いですよね。
音楽の楽しみ、それは「似ている曲」との出会い
こうして過去の記事を読み返してみると、私はどうやら「あの曲の雰囲気、なんか似ているなあ」「あのミュージシャンは、あのバンドの要素を上手く取り入れているなあ」と感じることに、特別な喜びを見出しているようです。
そこで今回は、音楽の楽しみ方のひとつ、「似ている曲」というテーマで筆を執りたいと思います。
「似ている曲」と聞くと、一部の日本のロックファンの方々は、すぐに「パクリか?」という言葉が頭をよぎるかもしれません。
しかし、私は「模倣」と「創造」は決して切り離せるものではないと考えています。
そのあたりの精緻な議論は、賑やかに路上ライブが行われているだろうニューオーリンズの街角に置いといて、まずは音楽そのものの面白さにフォーカスしていきましょう。
さて、今回のテーマは「ボ・ディドリー・ビート」を取り入れている楽曲たちです。
「似ている曲」というと、どうしてもメロディーの類似性が注目されがちですが、今回はビート、つまりリズムという観点から音楽の繋がりを探っていきたいと思います。
それは「ジャッ・ジャッ・ジャ・ジャッ・ジャ!」ボ・ディドリー・ビートとは?
「ボ・ディドリー・ビート」とは、その名の通り、ロックンロールのパイオニアであるボ・ディドリーが編み出したとされる特徴的なリズムパターンです。
一般的には、8分音符を基調とした、力強い手拍子のようなアクセントを持つビートで、「ジャッ・ジャッ・ジャ・ジャッ・ジャ!」という擬音で表現されることが多いです。
この独特のリズムは、アフリカの伝統的なリズムにルーツを持つと言われており、後のロックやポップスに大きな影響を与えました。
それでは、この特徴的な「ボ・ディドリー・ビート」がどのように様々な楽曲に取り入れられ、独自の魅力を生み出しているのか、具体的な例を7曲、見ていきましょう。
ドクター・ジョン(Dr.John)「IKO IKO」(1972年)
「イコ」ではなく「アイコ」と読みます。愛子さまのことでも、「あたしはカブトムシ」のことでもありません。
ニューオーリンズの奇才、ドクター・ジョンのアルバム「ガンボ(Dr.John’s Gumbo)」のオープニングを飾る、ノリノリの一曲のことです。
実はこの曲、オリジナルはドクター・ジョンではなく、ディキシー・カップス (The Dixie Cups)のバージョン(1964年)が有名です。
しかし、聴き比べてみると面白いことに、ディキシー・カップスのバージョンには、あの特徴的な「ジャッ・ジャッ・ジャ・ジャッ・ジャ!」のビートがありません。
ドクター・ジョンのバージョンを聴けば、「ボ・ディドリー・ビート」が楽曲に与える独特の推進力、グルーヴ感が一発で理解できるはずです。
星野源「ドラえもん」(2018年)
2曲目は、世代を超えて愛される国民的ミュージシャン、星野源さんです。
「SUN」(2015年)の頃は、「Prince好きの及川光博さんを少し地味にした感じの人が出てきたな」なんて思っていた時期もありましたが、その後「恋」(2016年)で大ブレイク。
国民的ミュージシャンの地位を確立しました。
さらに国民的アニメの主題歌を手掛け、その存在感を揺るぎないものにしたのは周知の通りです。
NHKの音楽番組「おげんさんと一緒」では、マエストロ細野晴臣さんとの親密な関係性もアピールし、そのクリエイティブな才能と大衆的な人気を両立させる稀有な存在感をさらに強固にしています。
そんな星野源さんの国民的アニメの主題歌「ドラえもん」は、イントロからまさしく「ボ・ディドリー・ビート」が炸裂しています。
どこか「笑点」のような雰囲気もミックスされているのが面白いですね。
そして、サビは一転して「ドドドドドドドドドッドー」という、跳ねるような勢いのあるメロディーラインが印象的です。
山下達郎「ドーナツ・ソング」(1996年)
星野源さんの紹介で細野晴臣さんの名前が出ましたので、3曲目はその盟友であり、大瀧詠一さんの弟子的存在でもある、山下達郎さんの楽曲をご紹介しましょう。
ミスタードーナツのCMのために書き下ろされたこの「ドーナツ・ソング」。
近年のミスドのCMでも菅田将暉さんがカバーしており、聴き覚えがある方も多いのではないでしょうか。
ともすれば商業主義的になりそうなところを、ブラック・ミュージックの王道とも言える「ボ・ディドリー・ビート」を大胆に取り入れることで、音楽好きをも唸らせるクオリティに昇華させている手腕は、さすがの一言です。
ポップでありながらも、しっかりと音楽的な深みを感じさせる、まさに達郎マジックと言えるでしょう。
大瀧詠一「1969年のドラッグレース」(1984年)
4曲目は、山下達郎さんの師匠筋にあたる、日本のポップスの巨匠、大瀧詠一さん。
彼の作り出す唯一無二のサウンド、「ナイアガラサウンド」が炸裂する名盤「EACH TIME」の収録曲です。
このアルバムはセールス的にも成功しており、作詞は名作詞家の松本隆さんです。
大瀧さん自身が作詞する曲には「びんぼう」(1976年)や「うららか」(1981年)のようなナンセンスな歌詞が多いのですが、全国民へのアピールを狙った楽曲には松本隆さんに作詞を依頼する傾向があるようです。
「1969年のドラッグレース」の特徴的なビートは、確かにブラック・ミュージックのそれですが、この曲での大瀧さんのボーカルスタイルやルックスは、どう見てもモンゴロイド。
前回の記事で触れた「あつさのせい」(1976年)のように、リズムを意識したネグロイド風な歌い方とは一線を画しています。
さらに面白いのがサビの後です。
「ジャ・ジャッ・ジャ・ジャッ・ジャ」という「ボ・ディドリー・ビート」に乗せて、続くのは意外なほどJ-POP的なギターソロ。
ブラック・ミュージック風のカッティングギターが来るかと思いきや、どこか懐かしい雰囲気のメロディアスなソロが展開されるのです。
この異質な組み合わせこそ、「日本のロック」を追求し続けた大瀧詠一さんの独特のセンスを感じさせます。
吉井和哉「クリア」(2014年)
この流れでまさかの登場、5曲目は吉井和哉さんです。
THE YELLOW MONKEY時代を含め、彼の音楽的なルーツはグラムロックやハードロック、そして日本の歌謡曲がメインだと思われがちで、シティ・ポップのような洗練されたイメージとは少し距離があるかもしれません。
しかし、意外なことに大瀧詠一さんとも無縁ではないのです。
肝心の楽曲「クリア」は、「1969年のドラッグレース」へのオマージュぶりに思わず笑ってしまうほど。
初めて意識的に聴き比べた時は「メインメロディーとギターソロの組み合わせとか、同じ曲じゃないか!」と雄叫びを上げたものです(じっくり聴き比べると違いは結構あるんですけどね)。
しかし、歌詞には「気分はボ・ディドリー」というフレーズがあるのですから、これはもう確信犯。
「やってますね!」と思わずニヤリとしてしまいます。吉井さんの遊び心と、音楽への深い愛情が感じられる一曲です。
U2「Desire」(1988年)
6曲目は、世界的ロックバンドU2の「Desire」です。
「Desire」に「ボ・ディドリー・ビート」が取り入れられているのは有名な話ですが、「なんでこの流れでU2?」と疑問に思う方もいるかもしれません。
実は、意外な繋がりがあるのです。
THE YELLOW MONKEYの「LOVE LOVE SHOW」(1997年)の英語詞バージョンで、ボーカルの吉井和哉さんは「U2 is getting too wise.」と歌っているんですね。直訳すると「U2は賢くなりつつある」といった意味合いでしょうか。「賢くなり過ぎている」の方が適切でしょうか。
世界的なビッグバンドであるU2も、その音楽の中に「ボ・ディドリー・ビート」を取り入れていることは、このリズムの普遍性と影響力を物語っていると言えるでしょう。
The Rolling Stones「Not Fade Away」(1964年)
最後にご紹介するのは、The Rolling Stonesの「Not Fade Away」です。
実はこの曲、オリジナルはBuddy Hollyの楽曲(1957年)で、ローリング・ストーンズによるカバーです。
Buddy Hollyのオリジナルバージョンは「ボ・ディドリー・ビート」ではありません。
ローリング・ストーンズのカバーを聴くと、彼らがこの楽曲に「ボ・ディドリー・ビート」を大胆に導入していることがよく分かります。
原曲と比較することで、「ボ・ディドリー・ビート」が楽曲の印象をどれほど変えるのか、その特徴をより深く理解することができるでしょう。
まとめ:グルーヴの連鎖。ボ・ディドリー・ビートが繋ぐ音楽の多様性
ここまで7曲ご紹介してきて、「ボ・ディドリー・ビート」という一つのリズムパターンを通して、時代やジャンルを超えた様々な楽曲が繋がっていることを見てきました。
何気なく聴いている音楽も、リズムという視点から深く掘り下げていくと、意外な発見や繋がりが見えてきて、さらに面白みが増すのではないでしょうか。
今回はリズムに焦点を当てましたが、メロディー、ハーモニー、歌詞など、音楽には様々な要素があり、それぞれの視点から「似ている曲」を探求してみるのもまた一興です。

それでは、また次回の音楽の記事でお会いしましょう!