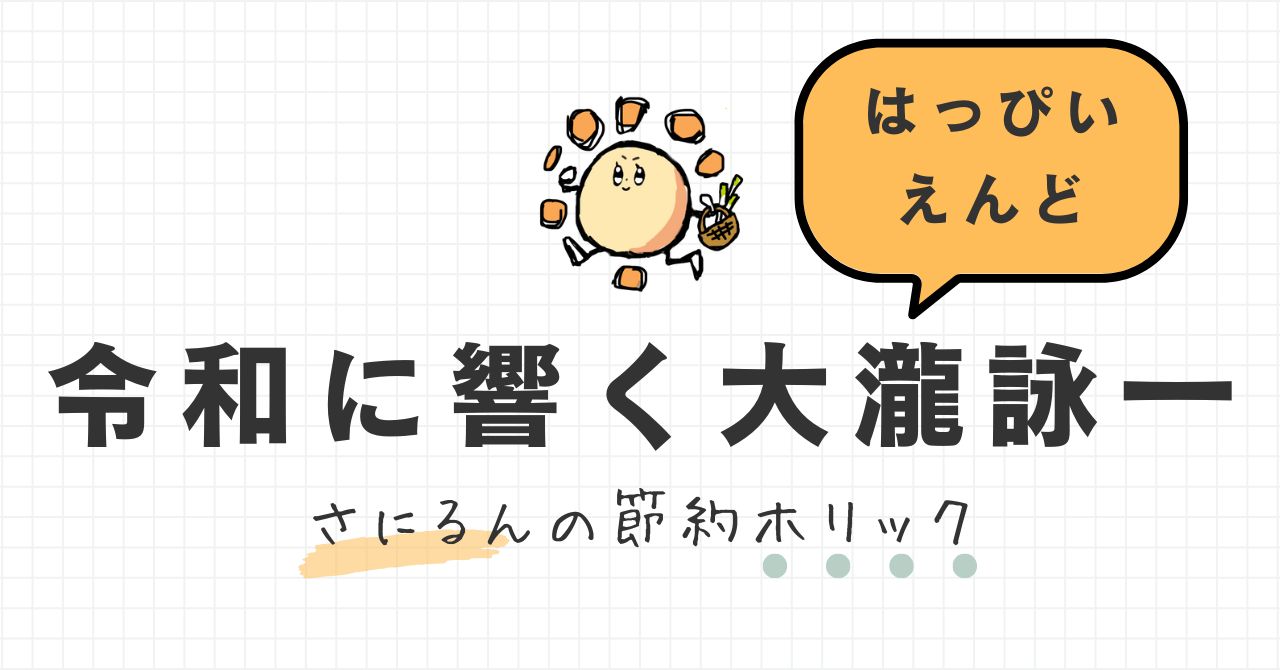配信全盛の時代ですが、CDで音楽を聴くのが好きで、音楽CDは1500枚以上持っています。
子ども達にも色々な音楽に触れてほしいので、一緒にいる時にもよく聴きます。
はっぴいえんどの「はいからはくち」が大好きで、たまにファンク・ロック風のライブバージョンや、あがた森魚バージョンと聞き比べたくなります。
いい音で聴きたくて、JBLのスピーカーやLUXMANのアンプを使っています。
日本語ロックの確立を語る上で、はっぴいえんどとサザンオールスターズは欠かせない存在だと思っています。
はっぴいえんどは、松本隆による「日本語で描く日本の情景」を、サザンオールスターズは桑田佳祐による「巻き舌と早口」を武器に、それぞれ独自のスタイルを確立しています。
しかし、日本語ロックの歴史において、もっとも注目すべきは、はっぴいえんどのメンバーでもある大瀧詠一のソロワークであると思っています。
大瀧詠一、天才的なリズム感の秘密
特に、アルバム「大瀧詠一」に収録されている「びんぼう」「ウララカ」「あつさのせい」の3曲は、日本語の持つ独特のリズムの難点、例えば、母音が多くロックのリズムに乗りにくい点、などを克服し、ロックのリズムに見事に融合させています。
これらの楽曲を聴くと、大瀧詠一が単なるポップスの範疇に収まらない、卓越したリズム感の持ち主であることがわかります。
はっぴいえんど時代の楽曲も素晴らしいですが、ソロ作品では、そのリズム感がより際立っていると思います。
インターネットもなかった1970年代において、大瀧詠一はすでに黒人音楽のリズムを自分のものにしており、自身の音楽に取り入れることに成功しています。
その革新的なリズム感は、当時の日本の音楽シーンにおいて異彩を放っていました。
独特なリズムを日本語の歌詞に自然に乗せる技術は、まさに天才の所業と言えるでしょう。
時代を超えて響く大瀧詠一の音楽
大瀧詠一のリズム感は、現代の音楽シーンにおいても色褪せることはありません。
我が家の子どもたちは、Mrs. GREEN APPLE(ミセスグリーンアップル)等の最近の音楽が好きでよく聴いていますが、ドライブの車内で「空とぶくじら」をかけると、こちらもまた、リズムに乗って聴いています。
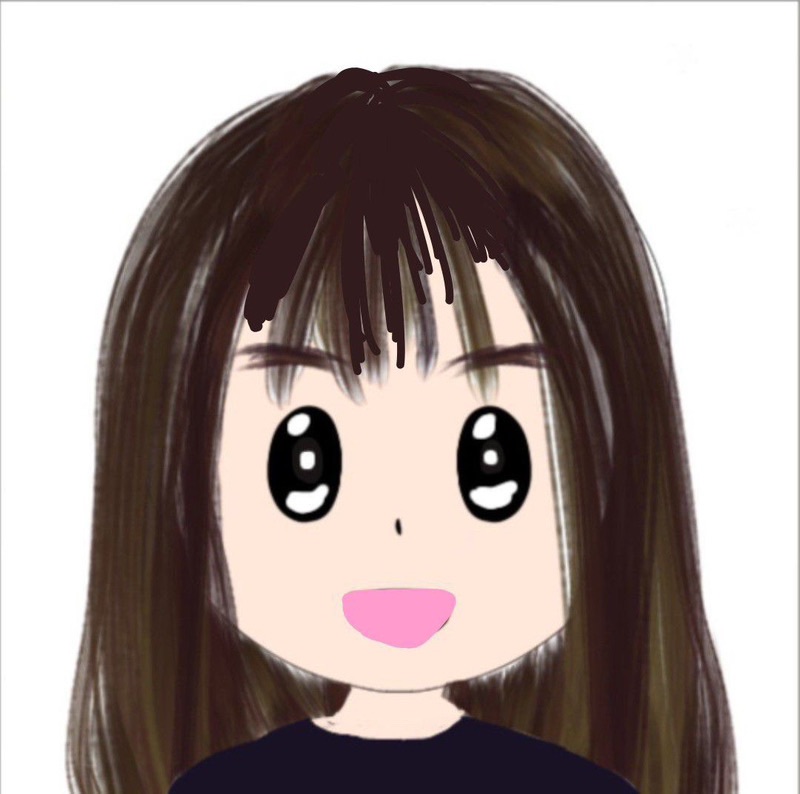
ちゃん♪ちゃん♪ちゃん♪ちゃん♪…
また、例えば、藤井風の楽曲には、大瀧詠一に通じるような、日本語の響きを活かした独特のリズム感を感じることができると思います。
藤井風の音楽が現代の人々を魅了するように、大瀧詠一の音楽もまた、時代を超えて聴く者の心を揺さぶる力を持っています。
令和ポップスへの影響と継承
大瀧詠一の音楽は、単なる懐古趣味で語られるべきものではありません。
彼の音楽は、日本語ロックの可能性を広げただけにとどまらず、シティポップが再評価されている現代の音楽シーンにも大きな影響を与え続けています。
日本語ロックを深く知りたいと思っている人にとっては、大瀧詠一の音楽は必聴と言えます。
まとめ・大瀧詠一の音楽に触れるということ
ここまで読んで下さり、日本語ロックに興味を持たれた方は、ぜひ大瀧詠一のソロアルバムを聴いてみてください。
彼の音楽は、きっとあなたの音楽観を大きく揺さぶり、広げてくれるはずです。