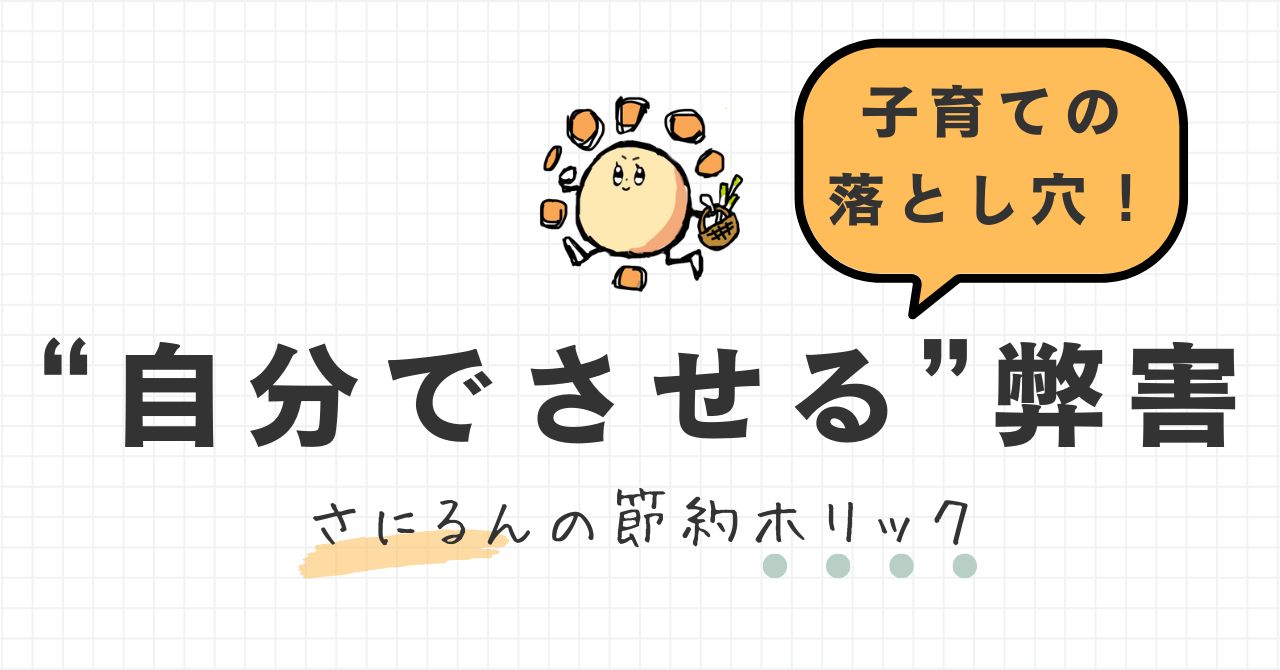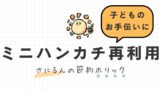この記事は以下の方におすすめです!
- お子さんに自立心を育んでほしいと思っている方
- 幼い頃から「自分のことは自分で」と徹底した結果、どうなったか気になる方
- 家族みんなで助け合うことの大切さを改めて考えたい方
こんにちは!子育て奮闘中のさにるんです。
「自分のことは自分でできるようになってほしい」親なら誰もが願うことですよね。
私もそう思い、幼い頃から子どもたちに「ごちそうさまして食器を自分で下げようね」「自分の洗濯物は自分でタンスにしまおうね」と教えてきました。
自立することは、子どもの成長において大切なことです。
しかし、今振り返ると、以前の私は、「自分のことは自分でやる」をただ徹底するやり方でした。
そして現在、どうなったか?…実は、子どもたちには、食器下げの習慣がまだあまりついていません。
また、思わぬ大きな弊害もあったと感じています。
散らかり放題の食卓が当たり前に?
数年前。
毎朝、我が家の子どもたちは、幼稚園バスの時間にギリギリでした。
朝食を食べ終えると、食器を片付ける余裕はなく、テーブルに置いたまま幼稚園へ行ってしまうことがしょっちゅう。
(そもそも、我が家の子どもたちは、現在でも「超」がつく面倒くさがりでかなり手強い…という要因もあります。)
私は、「自分で下げなさい」と言っている手前、親が片づけない方が良いと思い、食器を残しておき、帰宅後に「食器を下げてね」と声をかけていました。
(実際のところ、当時は私も離乳食の時期で忙しく、家族の食器を全部運んでテーブルを拭くまでの気力がなかった、という事情もあります。)
しかし、その結果、どうなったでしょうか?
昼食、夕食と時間が経つにつれて、なぜかテーブルにはどんどん食器が増えていったのです。
私がよく子どもを見ていると、「食器を下げて」と言うと、1つ2つは下げるけど、コップや食器がいくつか残ったままになっていたり、おやつの時間にまたコップを出してそのままになっていたり…。
夕食時には、テーブルには置き場がなくなり、

コップ何個あるの?使ってないものは下げて!
私が大きな声を出すと、子どもはやっと重い腰を上げて自分の食器を下げることもありましたが、まだ幼く、イヤイヤ言うこともありました。
こちらも時間がなく埒が明かないので、結局は、私が食器洗いの前にテーブルの食器を片づけることばかりでした。
私もキャパシティーを超えてしまい、離乳食がこぼれたテーブルを拭く気力すら失せるほどのカオス状態に……。
もしかしたら、子どもたちはあの時、「散らかっていても平気」という感覚を覚えてしまったのかもしれません。
当時、私は、「毎日していたら、そのうちできるようになるだろう」と考えていました。
しかし、小さな子どもたちにはまだ難しく、大人が考えるよりも食器が多く見えて、ハードルが高く感じてしまったのかもしれません。
その結果、「自分のことは自分で」とは程遠い状況になってしまっていました。
幼い子どもに対し、杓子定規に自分で食器を下げさせるのではなく、親が「一緒に運ぼうね」と手伝ったり、テーブルに残しておくにしても数を減らしておいたり、もっとサポートが必要だったと反省しています。
「自分のことだけ」が加速した弊害
さらに、もっと心配な弊害がありました。それは、「自分のもの」と「他人のもの」を明確に区別し、「自分のこと以外はやらない」という意識が芽生えてしまったかもしれないことです。
さて、現在。
子どもたちも成長し、数年前の幼児期に比べると、私が声をかけたら食器を下げてくれるようにはなってきました。
ですが、例えば、夕食後、私が「食器を運んでくれる?」と声をかけると、子どもは自分の空になったお皿を持ってきます。
「ついでにお父さんのもお願いできる?」と声をかけると、ちょっと嫌な顔をして「えー、なんでお父さんがしないの?」と言うのです。
渋々持ってきてはくれますが、少しの手間をかけるだけで一緒に運ぶことができるのに、それを面倒がってしまいます。

小さい頃から、私が「自分でやりなさい」と言い過ぎたせいなのかな……
親が子どもを手伝わないスタンスをとったことで、子どもたちは「自分のことは自分で。それ以外のことをやるのは損」と学習してしまったのかもしれません。
他の人の状況を察したり、忙しい家族の手助けをすることに抵抗を感じたりするようになってしまったのではないか…?と、少し心配しています。
今からでも遅くない!家族で「助け合い」を育む
もちろん、「自分でできること」自体は、やはり大切だと思います。
しかし、それ以上に大切なのは、家族というチームの中で互いを思いやり、支え合う心ではないでしょうか。
考えを改めてからは、「自分のことは自分で」のスタンスを、少し形を変えて実践しています。
朝、子どもたちが忙しくて時間がとれないときは、
「遅刻するよ!お母さんがお皿運んでおくから、気をつけていってらっしゃい」と声をかけて、「あなたのことを手伝うよ」というメッセージを伝えるようにしています。
その結果、この先どうなるか?
…子育ての答え合わせは簡単にはできませんが、私がこのことで考えたのは、自立した、思いやりのある子に育ってほしいなら、親が手をかけ、思いやりを見せる必要があるだろうということです。
もちろん、子どもたちへ。時には、夫婦同士で。声をかけ合う姿を見せる。
そして、食器を全部下げて、テーブルも、いつもきれいに拭いておく。
子どもたちも、お願いすると、テーブル拭きのお手伝いをしてくれたりします。
少しずつですが、忙しい人やできない人がいたら、家族みんなで助け合うことを当たり前の習慣にしていきたいと思っています。
「お父さん、疲れてるみたいだから、一緒に洗い物しようか?」
「お母さん、手が離せないみたいだから、洗濯物畳んでおくね!」
そんな温かい言葉が自然と飛び交う家庭を目指して。
最後に:「正解」はない。それぞれの家庭で子どもと向き合おう
今回の記事では、あくまで一つの事例として、我が家のお話をご紹介しました。
子どもは一人一人みんな違いますし、同じ経験をしても、その子によって結果は色々違ってくると思いますので、ご紹介した方法が絶対正しい・間違っているということは分かりません。(そもそも、我が家の子どもたちは「超」がつく面倒くさがりです…。)
ただ、少子化の昨今、親のしつけに厳しい風潮がありますが、親が何かを一生懸命教えたとしても、必ずしも子どもができるようになる訳ではないことは確かです。
子育てについては、「これが一番良い」と決めつけ過ぎず、それぞれの家庭で子どもと向き合いながら考えていくことが大事だと思っています。
最後に、今回の記事のポイントはこちら!
- 「自分のことは自分で」を徹底しても、ハードルが高すぎると出来るようにならない。子どもの段階に合わせて親がサポート。
- 幼い頃からの徹底が、忙しい家族への手助けや思いやりを育てることを阻む可能性も。
- 今からでも遅くない。家族は助け合うチーム。家族で助け合うことの喜びを共有し、温かい家庭を築こう。
最後まで読んで頂き、ありがとうございました。